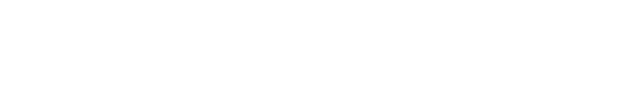足関節の痛み
スポーツ中の足関節の痛み
スポーツを楽しんでいる時に、足首に痛みを感じることはありませんか?足首(足関節)は、私たちの体重を支えたり、走ったり、跳んだり、方向転換したりと、スポーツをする上でとても大切な役割を担っています。そのため、大きな力がかかりやすく、ケガをしやすい場所でもあります。足首の痛みには、捻挫や疲労骨折、腱(けん)の炎症など、様々な種類があります。正しい診断と適切な治療を受けることで、痛みを和らげ、また安心してスポーツに戻れるようになります。
足関節の痛みの症状について
足首の痛みは、何が原因で起きているかによって、出方が変わってきます。
- 急に起こる痛み:捻挫(ねんざ)や骨折のように、何かきっかけがあって急に痛み出すものです。ケガをした直後からズキズキと強く痛み、足首が腫れたり、熱を持ったりすることがあります。体重をかけると痛みがひどくなり、歩くのが大変になることもあります。
- だんだん強くなる痛み(慢性的な痛み):使いすぎや、小さな負担が繰り返しかかることで、少しずつ痛みが出てきて、長く続くことがあります。運動中だけ痛んだり、朝起きた時に足首がこわばる感じがしたりすることもあります。痛みが軽めでも、練習や試合を続けると、だんだん悪化していく傾向があります。
- 特定の動きで痛む:ジャンプして着地した時、急に方向を変えた時、ダッシュした時など、特定のスポーツの動きで痛みが強くなることがあります。これは、その動きで足首の特定の場所に負担がかかっているサインです。
- 押すと痛む(圧痛):痛む場所を押すと、さらに痛く感じます。どこを押すと痛いかで、足首のどの部分が傷ついているかのヒントになります。
- 腫れ、熱っぽさ、赤み:足首に炎症が起きている時に見られる症状です。特にケガをしたばかりの時は、はっきりと現れることが多いです。
- 動かしにくい(可動域制限):足首を動かせる範囲が狭くなります。痛みのためだったり、関節の中の組織が腫れることで動きが制限されたりすることがあります。
- ぐらつく感じ(不安定感):足首がグラグラしたり、力が入りにくいと感じることがあります。靭帯(じんたい)という、骨と骨をつなぐゴムのような組織が傷ついたり、関節が緩んでしまったりすることが原因で起こります。
- しびれ:まれに、神経が圧迫されたり傷ついたりすることで、足のしびれを伴うこともあります。
これらの症状は、どんなスポーツをしているかや、どれくらい運動しているかによっても違ってきますし、いくつかの症状が同時に現れることもよくあります。
足関節の痛みの診断方法について
足首の痛みがなぜ起きているのかを正確に突き止めるためには、専門のお医者さんによる様々な検査が必要です。
- 問診:
- いつから痛みがあるのか、どんな時に痛くなったのか(急に痛くなったか、だんだん痛くなったか)。
- 痛む場所、どんな痛みか(鋭い痛み、鈍い痛み、ズキズキする痛みなど)、どのくらい痛いか。
- 痛みが強くなる動きや、楽になる動き。
- 今まで足首をケガしたことがあるか。
- どんなスポーツを、どれくらいの頻度でしているか。 こうしたお話から、痛みの原因を探るための手がかりを見つけます。
- 視診・触診(見て触ること):
- 足首が腫れていないか、熱を持っていないか、赤くなっていないか、形がおかしくないかを見ます。
- 痛む場所を実際に触ってみて、押すと痛い場所や、いつもと違う熱っぽさ、しこりがないかなどを確認します。骨の出っ張りや、腱の通り道などもチェックします。
- 理学検査(体を動かしてもらう検査):
- 足首をどれくらい動かせるか(つま先を上げ下げする、内側や外側にひねるなど)を測り、動きが制限されていないか、どの角度で痛むかを確認します。
- 靭帯が傷ついていないかを調べるために、足首を特定の方向に動かしたり引っ張ったりする検査(「前引き出しテスト」や「内反ストレステスト」など)を行います。これで、特定の靭帯が緩んでいるか、どの程度傷ついているかを判断します。
- 腱の損傷や炎症を調べるために、足首に力を入れてもらう検査も行います。
- 画像検査:
- X線検査(レントゲン):骨折や、骨の一部がはがれた「剥離骨折」、関節の変形、関節の隙間が狭くなっていないかなどを確認するために行います。
- MRI(磁気共鳴画像法):骨だけでなく、軟骨、靭帯、腱、筋肉、関節を包む膜などの柔らかい組織(軟部組織)の状態を詳しく見ることができます。捻挫による靭帯の傷の程度、腱の損傷、軟骨の損傷、疲労骨折、関節の膜の炎症などを診断するのにとても役立ちます。
- 超音波検査(エコー):リアルタイムで柔らかい組織の状態を観察でき、動かしながら診ることもできます。腱の炎症や切れている部分、関節の膜の炎症、足の裏の筋膜炎などの診断に役立ちます。
これらの検査を組み合わせて、痛みの正確な原因を特定し、最適な治療計画を立てていきます。
足関節の痛みの原因について
スポーツ中に足首が痛くなる原因はたくさんありますが、大きく分けて「外傷によるもの」と「使いすぎによるもの」に分けられます。
- 外傷による原因:
- 足関節捻挫:スポーツ中のケガで最も多いものの一つです。足首が内側や外側に不自然にひねられることで、関節を支えている靭帯が傷つきます。特に、足首を内側にひねって起きる「内反捻挫」が多く、足首の外側の靭帯(前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯)が傷つきます。靭帯が伸びただけなのか、一部が切れたのか、完全に切れてしまったのかで重症度が変わります。
- 骨折:
- 足関節骨折:スネの骨(脛骨)や腓骨(ひこつ)の足首に近い部分の骨折で、転んだり、ぶつかったりといった大きな力で起こります。
- 疲労骨折:走ったり、ジャンプしたりを繰り返すことで、骨に小さな負担がかかり続け、骨の修復が追いつかずに骨が折れてしまうものです。長距離ランナーやジャンプを多くする選手に多く、脛骨、腓骨、舟状骨(しゅうじょうこつ)、中足骨(ちゅうそくこつ)などにできやすいです。
- 剥離骨折:靭帯や腱が骨にくっついている部分が、強い力で引っ張られて、骨のかけらと一緒に剥がれてしまう骨折です。
- 軟骨損傷:転んだり捻挫したりすることで、関節の表面にある軟骨に直接衝撃が加わり、軟骨が欠けたり傷ついたりすることがあります。特に、足首の関節を構成する距骨(きょこつ)という骨の軟骨が傷つく「離断性骨軟骨炎」は、スポーツ選手によく見られます。
- アキレス腱断裂:急にダッシュしたりジャンプしたりした時に、アキレス腱に強い負荷がかかって切れてしまうことがあります。
- 使いすぎによる原因(非外傷性):
- アキレス腱炎/アキレス腱周囲炎:ランニングやジャンプ動作の繰り返しによって、アキレス腱そのものや、その周りの組織に炎症が起きる病気です。かかとからふくらはぎにかけて痛むのが特徴です。
- 脛骨過労性骨膜炎(シンスプリント):スネの内側の骨に沿って痛みが生じるもので、ランニングやジャンプを多くする選手によく見られます。スネの骨につく筋肉や骨膜に炎症が起こることで発生します。
- 足底筋膜炎:足の裏にある足底筋膜という腱のような組織に炎症が起きる病気です。特にかかとや足の裏の土踏まずの部分に痛みが生じます。長時間立っていたり、ランニングなどで足に負担がかかることで発症します。
- 三角骨障害(後方インピンジメント症候群):足首を底屈(つま先を下げる)する動作を繰り返すことで、距骨の後ろにある「三角骨」(あるいはそれに似た骨の出っ張り)とスネの骨や踵の骨がぶつかり、炎症や痛みを引き起こします。バレエダンサーやサッカー選手などに多く見られます。
- インピンジメント症候群(衝突性症候群):足首の前の部分や後ろの部分で、骨のトゲ(骨棘)や柔らかい組織が挟み込まれることで痛みが起こります。過去に捻挫をしたことがある場合や、繰り返しの負担が原因となることがあります。
- 変形性足関節症:足首の関節の軟骨がすり減ってしまい、関節が変形することで痛みが起こる病気です。過去にひどい捻挫や骨折をしたことがある人に多いです。
- 滑膜炎:関節を包む「滑膜(かつまく)」という膜に炎症が起き、痛みや腫れを引き起こします。使いすぎや、関節の中にある小さな軟骨片などが原因となることがあります。
足関節の痛みの治療法
足首の痛みの治療は、痛みの原因や重症度、患者さんがどのくらいスポーツをしたいか、どんな目標を持っているかによって変わってきます。まずは手術をしない方法(保存的治療)から始めますが、それでも良くならない場合や、ひどいケガの場合は手術が必要になることもあります。
- 保存的治療(手術をしない治療):
- お薬での治療:
- 痛み止めや炎症を抑える薬:炎症や痛みを抑えるために、飲み薬や湿布、塗り薬が処方されます。
- 注射:炎症が強い場合や痛みが特定の場所にある場合に、ステロイドなどを関節の中や腱の周りに注射することがあります。
- 物理療法:
- 電気治療:低周波や超音波などを使って、痛みや炎症を和らげ、血行を良くします。
- 温める・冷やす治療:症状に合わせて温めたり冷やしたりすることで、血行を良くしたり、痛みを和らげたりします。
- 超音波治療:炎症を抑えたり、温めたりして痛みを和らげます。
- 装具での治療:
- テーピング:足首をしっかり固定し、特定の動きを制限することで、痛みを減らし、再びケガをするのを防ぎます。
- サポーター:足首を保護し、安定させます。特に捻挫の後や、足首がぐらつく感じが残る場合に有効です。
- インソール(足底板):靴の中に入れる中敷きで、足のアーチを支え、足首にかかる負担を減らします。足の形や歩き方の癖を直すことで、痛みの根本原因にアプローチすることもあります。
- リハビリテーション:
- ストレッチ:硬くなった筋肉や関節の動きを良くします。
- 筋力トレーニング:足首周りの筋肉を強くして、関節の安定性を高めます。特に、足首の外側の筋肉を強くすることは、捻挫の再発予防にとても大切です。
- バランス訓練:不安定な台の上で片足立ちをするなどして、足首が自分の位置や動きを感知する能力(固有受容覚)を高め、バランス感覚を養います。これは、ケガの再発を防ぐために非常に重要です。
- フォーム指導:スポーツの動き方を分析し、足首に負担がかかりにくい、効率的な体の使い方をアドバイスします。
- 手術での治療:
保存的治療で痛みが良くならない場合や、靭帯が完全に切れてしまっている、足首がひどく不安定な場合、重い軟骨の損傷、大きな骨折など、特定の病気に対しては手術が検討されます。
- 靭帯再建術:重度の靭帯損傷で足首の不安定さが続く場合に、自分の腱の一部や人工的な靭帯を使って、新しい靭帯を作り直します。
- 関節鏡(かんせつきょう)手術:小さな傷口からカメラを入れ、足首の中を見ながら、傷ついた軟骨の治療(小さな穴を開けて軟骨の再生を促すなど)、邪魔なかけらの除去、骨のトゲの切除、炎症を起こした膜の切除などを行います。体への負担が少なく、回復が比較的早いのが特徴です。
- 骨切り術:足首の変形が進み、骨の位置がずれている場合に、骨を切って角度を調整することで、関節にかかる負担を減らします。
- 骨接合術:骨折した部分をプレートやネジなどで固定し、骨がくっつくのを助けます。
手術の後は、専門的なリハビリテーションが欠かせません。少しずつ運動の量を増やしていき、筋肉の力、足首の動く範囲、バランス能力を回復させ、最終的には安全にスポーツに復帰できるようサポートします。
足首の痛みは、放っておくと痛みが長引いたり、体の他の場所に影響が出たりする可能性があります。スポーツ中に足首に痛みを感じたら、決して軽く見ずに、早めにスポーツ整形外科を受診して、適切な診断と治療を受けることが大切です。当クリニックでは、患者さん一人ひとりの症状と、どれくらいスポーツをしたいかという目標に合わせて、一番良い治療計画をご提案し、またスポーツを楽しめるようになるまでお手伝いさせていただきます。